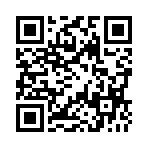「NPOの未来」を学び、議論する!
2010年05月17日
地球市民の会 第9回通常総会記念イベント 地球市民の会会員大討論
会 ~NPOの未来を考える―今、地球市民の会は何ができるのか?~
どうして?教えて!大串政務長官!
財務省の政務官に、聞いてみよう!たずねてみよう!
私たちの暮らし、私たちの未来!
CSOポータルのメーリングリストで流れてきた情報で、
「あっ!聞きに行かなきゃ!」
と思った討論会でした。
ちょうどお休み日曜日でしたので、リフレッシュも兼ねてアバンセまで行ってきました。
私の今のテーマは「新しい公共」
そのことで少しでもえるものがればと思いました。
川北氏の勉強会でもありましたが、事業の移譲だけではなく、「権限」と「予算」の移譲が必要。
内閣府で「新しい公共円卓会議」が行われています。
こういったことを注視する事も、自分たちでできることを模索する事も大切だと思います。
新しい公共円卓会議の資料
この中に取りまとめに向けての資料も入っています。
実際にはどうなるんでしょうね。
会 ~NPOの未来を考える―今、地球市民の会は何ができるのか?~
どうして?教えて!大串政務長官!
財務省の政務官に、聞いてみよう!たずねてみよう!
私たちの暮らし、私たちの未来!
CSOポータルのメーリングリストで流れてきた情報で、
「あっ!聞きに行かなきゃ!」
と思った討論会でした。
ちょうどお休み日曜日でしたので、リフレッシュも兼ねてアバンセまで行ってきました。
私の今のテーマは「新しい公共」
そのことで少しでもえるものがればと思いました。
川北氏の勉強会でもありましたが、事業の移譲だけではなく、「権限」と「予算」の移譲が必要。
内閣府で「新しい公共円卓会議」が行われています。
こういったことを注視する事も、自分たちでできることを模索する事も大切だと思います。
新しい公共円卓会議の資料
この中に取りまとめに向けての資料も入っています。
実際にはどうなるんでしょうね。
5月16日 地球市民の会 第9回通常総会記念イベント 地球市民の会会員大討論会
~NPOの未来を考える―今、地球市民の会は何ができるのか?~
どうして?教えて!大串政務長官!
財務省の政務官に、聞いてみよう!たずねてみよう!
私たちの暮らし、私たちの未来!
社会の仕組みが大きく変わってきた2010年。今までと違う社会の在り方の中でNPOとしての地球市民の会は何ができるのか、を会員の皆様とともに、学び、考えていきます。
財務大臣政務官と佐賀県知事と一緒に「NPOの未来」を学び、議論する
◎論客 大串博志財務大臣政務官(衆議院員)
◎コメンテーター 古川康(佐賀県知事)
◎代表質問者 佐藤昭二(地球市民の会会長)
山口久臣(地球市民の会副会長)
◎コーディネーター 山下雄司(地球市民の会理事長)
テーマ1「新しい公共」におけるNPOの有効性について
最近よく聞く言葉=「新しい公共」、そもそも「公共」って何?「新しい」って、何が新しいの?それでそれは、どんなNPOにとってもチャンスなの?
大串氏
人と人が支え合う新しい公共の概念。公の仕事を行政だけがするのではなく、いろんな人で行えないか?と言うこと。
例えば・・・消防団、自治会など
税を払うことで公共に貢献しているが、それ以外に出来ないか?(体を動かしてする貢献)→新しい公共
スウェットエクイティー→自分の行動アクションを持って貢献する。
円卓会議で話し合いをしている。
5月末までに取りまとめをしていく。
NPOの方々にとっての税制・制度の規制緩和など
質問 山口氏
ヨーロッパでの公の考え方が進んでいる。
ヨーロッパの公園がきれいなのは私も汚さないからみなさんも汚さないでという暗黙の了解ができている。
日本は自分の周りが綺麗ならいい→ごみを掃き出すという考え方。
協働、パートナーシップ、適材適所という考え方が日本では根付かない。スローガンのみ。
持っている力、違うものをコーディネートしていく仕組みがドイツにはある。
さて、日本の円卓会議の目的は?
大串氏
日本ではなかなか協働が進んでいかない。それをどうすればいいのかを考える。
税制、NPO、公益法人にするハードルを下げるため。
佐藤氏
改めてボランティアというのが分からない。元々日本はボランティアだったのでは?
大串氏
途上の地域では隣組などの組織が機能しやすいが、先進地ではそれが機能しなくなているので日本はそれを考え直す時になっている。
山口氏
政府はNPOが新しい公共を担えると思っているのか?
大串氏
政府さえしっかりすればかなり多くのNPOが担えるのではないかと考えている。
古川
しっかりとした資料づくりがうれしい。
勉強になると思うのでみたい方は地球市民の会に問い合わせた方が良いと思う(大野さんが資料を作られていた。)
本格的に行政と真剣に協働していこうという流れは間違いない。
税制が変われば・・・税収が減ることは問題。
そのことも考えなければならない。
もともと「七人の侍」的なことを日本はしていた。自分たちでできることは自分たちでしようと!戦後なくなった。
昔は義務でしていた。今は志で行っている。(佐賀県ではCSOと呼んでいる)
佐賀県の協働化テストは国連の公共サービスのオリンピックでは昨年度は最終審査まで残ったが、選ばれなかった。今年も最終審査まで残っている。それだけ認められている手法であるといえる。
佐賀県は消防団の組織率が№1である。有田町では今右衛門さんも出初め式では行進していた。
こういったことが良いのではないか?
テーマ2「NPO法人に対する寄付控除制度」の現状と課題
大串氏
NPOの財政基盤をしっかりするため。
認定NPOを浮揚して税制の優遇をしてきた。
認定NPOのハードルが高い。寄付・会費・事業収入・助成金
公的な収入の割合が20%以上ないと認定されない。
寄附金の額は少なくとも多くの人が寄付してくれたらいいのではないか?
しかし、今の制度では認定されない。
新しいNPO→すぐには認定されない→寄付が集まらない→・・・・仮認定という考え方
まず、仮認定してから寄付を集めやすくし、それから本認定という形をとれるようになれば立ち上げたすぐのNPO法人も寄付を集めやすくなるのではないか?
今までは国税局が認定していたが、地域で認定できるようになることが大切ではないか?
公益法人→6か月かかるものを3-4カ月で認定できるようにする。
以上のようなことを考えている。
質問
佐藤氏
認定NPO法人、公益法人に寄付した時のメリットは?
大串氏
今までは所得控除
所得控除は所得の高い人ほど有利になった。
税額控除に変えることができないか?と議論している。
沢山の人が寄付してくれるようにするため、すそ野を広げたい。
山口氏
日本人はなるべく税金を払いたくないと思っている。
税金の控除をすることによって税収が落ちるのではないか?借金が増えることをどう考えるか?
大串氏
税収に対してマイナスになるが、公の仕事をみんなでしていくことで行政がしているしごとをNPOがするか、行政がするか選べるようになる。
そのことで財政的にはニュートラルになって欲しいと望む。
日本はギリシアに近い。行政がしていることで無駄になっていることをNPOがすることで有効なことになればいい。
古川氏
ふるさと納税が3年目になった。これは税額控除である。佐賀県は実額全国で20位くらいだが、人口を考慮するとかなりの額だといえる。大口の寄付も多い。
たとえば3,500万円とか1,000万円とか。
個人と社会の関係を考える税制。
自分が考えるものに支払う。税金も選べるようになる。
税収が減るのは意味のあること。無駄を減らそうとするのではないか?
報告があったりと信頼できる所にお金を出す。
例えば、
海外で災害があった時、佐賀県では見舞金を出すようにしている。
今までは日赤を通して寄付をしていた。
しかし、何に使われているか分からないので今度はユニセフに寄付した。
それでも何に使われているか分からなかった。
その次はフィリピンだったこともあり、地球市民の会に寄付した。
地球市民の会は佐賀県が出した見舞金を何の事業に使い、何ができたのかという報告書を出してくれた。
こうしたことをしたのは地球市民の会だけだった。
寄付を受けたからにはNPOにも報告責任があると思う。
テーマ3 「道州制と地方分権、地方主権」とNPOが果たすべき役割
道州制と地方分権、地方主権って違うの?一緒ではないの?国が地方に自分たちのことは自分たちで決めさせようってことなんでしょ?
大串氏
地域主権戦略会議を原口大臣を中心として考えている。
日本は中央集権。今までは機能していたが、現在は地元のことは地元で決めていくことという原則があって、補完性の原則がある。
コミュニティーで決められるものはコミュニティーで決める。
↓
コミュニティーで決められないことは市町、
↓
市町で決められないことは県、
↓
県で決められないことは国
↓
国に残ることは外交などだけになる。
近い人が決めていく。地元が権限を持っていく。
23年度は補助金を一括で地方へ交付し地方で何に使うか決めてもらう。
その受け皿は何が良いのか、道州制or県
地域主権を考えて、行動していくとだんだんと適正な規模が分かるのではないか?
大切なのは私たちが決められるということ。
税の納め先も、何に使うかも選べることも大切。
質問
佐藤氏
・管大臣は地域主権を進めているが、平成の大合併に反するのではないか?
・ミャンマーの子どもたちにひかれるのはなぜか?かわいそうだけではない。先祖や親を敬う気持ちを持っているからだ。そこが美しい。それに祈りがある。NPOの在り方もそこにあるのではないか?
・「農」を基本に学ぶ必要があるのではないか?
大串氏
小規模分散、平成の大合併。もう少し見ていかないと正確な答えは出ないのではないか?
小規模分散は自然の摂理、補完の原則。どの行政でどのくらいの大きさが必要か?これから分かってくるのではないか?
必要な財源、権限を地域の移譲していくことで分かるのではないか?
ベンチャーの人々で成功している人の話を聞くとデジタル的なことよりもアナログ的なこと、熱意や想いが大切だと言っている。
NPOでなければ背負えないものは熱さ、情念。これは行政では無理。
山口氏
大規模災害が起こる可能性が日本にはある。
関東大震災、富士山の噴火、東海地震、こういったことが起こると日本すべてがダメになる。
その前に独立した方が良いのではないか?
九州規模の独立国家だってある(デンマークやスイスなど)
九州自身が力をつけていくことが大切。ドミノ倒しにならないように。
大串氏
権限、財源が地域に戻されるとおさまりの良い規模になる。
それは道路、通信の規模だと思う。
古川氏
道州制・・・良いんじゃない?
でも下手をすると国家による地域分割になる可能性もある。
明治より日本は合併を繰り返している。しかし、県だけは変わっていない。
今のままでいいという理屈がわからない。
特区を国に訴えても通らない。権限よりも欲しいもの、それは責任。
県だけでは難しいことも、九州くらいなら出来ることもある。
目に見えるところでの節約やお金を出すことはできても、見えないものだと納得できない。
日本は超高齢者社会だが、ノルウェー、スウェーデン並みの消費税の税率は出来ない。
それは決める機関があまりにも遠すぎて見えないから。
ノルウェー、スウェーデンの人口だからこそ近くで決められていることが見えるので納得できている。
佐賀は道州制を引っ張って行っている。
議論の中心になって行かないといけない。九州モデルは佐賀県が作った。それが国のモデルになっている。
甲子園で応援するくらいの規模が妥当ではないか?((笑))
基礎自治体への財政と権限の移譲から始まっていくのではないか?
質問
(東京からの参加者)
税の控除は確定申告or年末調整?
出来れば年末調整にして欲しいのだか。
大串氏
日本は分かりずらい。アメリカは全員が確定申告をしなければならない。
今の日本のインフラでできるのは年末調整だと思う。調整改革が必要。
(熊本からの参加者)
税金の説明
年収300万円の人が12,000円の会費(寄付)を支払うとする
税金を10%とすると300万円×10%=30万円
認定NPO法人以外だと12,000円払っても何の税の控除はない。
これが認定NPO法人になると(税額控除)
300万円-12,000円=298万8千円
298万8千円×10%=29万8千円
30万円-29万8千円=1,200円
1,200円が税金から控除される。税金として支払うのは29万8千円
もし、税金分の30万円を寄付したとする
300万円×10%=30万円
寄付した金額の50%が控除されるので
15万円を税金として払うことになる。
もしこれが所得控除なら
300万円-30万円=270万円
270万円×10%=27万円
税金として27万円支払うことになる。
30万円は寄付しているので最終的には
税額控除では45万円(寄付+税金)
所得控除では57万円(寄付+税金)支払うこととなる。
最後に
山口氏
政治家でも行政マンではなくNPOが税金について半分でも使い道を考えられつようになることが新しい公共になるのではないか?
古川氏
程よい政府を目指すには協働をしていかなくてはいけない。
協働化テストはコスト削減ではなく県民満足度の向上が目的。
何でも小さくすることが良いとは思わない。
我々がしなければならないことをすべき。減らすことだけを目的としてはいけない。
協働機関の設置。(国会で原口大臣が提案している)
合併しなくても合併の効果を上げるもの
大串氏
共有したいもの、それは国民一人一人が自分たちで選択する時代になってきているということ。
国、県が何をしてくれるか?ではなく、自分自身が何をすべきか。を考えるべき。
NPOがそれを担っている。
私たちは何ができるのかという思いを拡げていかなくてはいけない。
~NPOの未来を考える―今、地球市民の会は何ができるのか?~
どうして?教えて!大串政務長官!
財務省の政務官に、聞いてみよう!たずねてみよう!
私たちの暮らし、私たちの未来!
社会の仕組みが大きく変わってきた2010年。今までと違う社会の在り方の中でNPOとしての地球市民の会は何ができるのか、を会員の皆様とともに、学び、考えていきます。
財務大臣政務官と佐賀県知事と一緒に「NPOの未来」を学び、議論する
◎論客 大串博志財務大臣政務官(衆議院員)
◎コメンテーター 古川康(佐賀県知事)
◎代表質問者 佐藤昭二(地球市民の会会長)
山口久臣(地球市民の会副会長)
◎コーディネーター 山下雄司(地球市民の会理事長)
テーマ1「新しい公共」におけるNPOの有効性について
最近よく聞く言葉=「新しい公共」、そもそも「公共」って何?「新しい」って、何が新しいの?それでそれは、どんなNPOにとってもチャンスなの?
大串氏
人と人が支え合う新しい公共の概念。公の仕事を行政だけがするのではなく、いろんな人で行えないか?と言うこと。
例えば・・・消防団、自治会など
税を払うことで公共に貢献しているが、それ以外に出来ないか?(体を動かしてする貢献)→新しい公共
スウェットエクイティー→自分の行動アクションを持って貢献する。
円卓会議で話し合いをしている。
5月末までに取りまとめをしていく。
NPOの方々にとっての税制・制度の規制緩和など
質問 山口氏
ヨーロッパでの公の考え方が進んでいる。
ヨーロッパの公園がきれいなのは私も汚さないからみなさんも汚さないでという暗黙の了解ができている。
日本は自分の周りが綺麗ならいい→ごみを掃き出すという考え方。
協働、パートナーシップ、適材適所という考え方が日本では根付かない。スローガンのみ。
持っている力、違うものをコーディネートしていく仕組みがドイツにはある。
さて、日本の円卓会議の目的は?
大串氏
日本ではなかなか協働が進んでいかない。それをどうすればいいのかを考える。
税制、NPO、公益法人にするハードルを下げるため。
佐藤氏
改めてボランティアというのが分からない。元々日本はボランティアだったのでは?
大串氏
途上の地域では隣組などの組織が機能しやすいが、先進地ではそれが機能しなくなているので日本はそれを考え直す時になっている。
山口氏
政府はNPOが新しい公共を担えると思っているのか?
大串氏
政府さえしっかりすればかなり多くのNPOが担えるのではないかと考えている。
古川
しっかりとした資料づくりがうれしい。
勉強になると思うのでみたい方は地球市民の会に問い合わせた方が良いと思う(大野さんが資料を作られていた。)
本格的に行政と真剣に協働していこうという流れは間違いない。
税制が変われば・・・税収が減ることは問題。
そのことも考えなければならない。
もともと「七人の侍」的なことを日本はしていた。自分たちでできることは自分たちでしようと!戦後なくなった。
昔は義務でしていた。今は志で行っている。(佐賀県ではCSOと呼んでいる)
佐賀県の協働化テストは国連の公共サービスのオリンピックでは昨年度は最終審査まで残ったが、選ばれなかった。今年も最終審査まで残っている。それだけ認められている手法であるといえる。
佐賀県は消防団の組織率が№1である。有田町では今右衛門さんも出初め式では行進していた。
こういったことが良いのではないか?
テーマ2「NPO法人に対する寄付控除制度」の現状と課題
大串氏
NPOの財政基盤をしっかりするため。
認定NPOを浮揚して税制の優遇をしてきた。
認定NPOのハードルが高い。寄付・会費・事業収入・助成金
公的な収入の割合が20%以上ないと認定されない。
寄附金の額は少なくとも多くの人が寄付してくれたらいいのではないか?
しかし、今の制度では認定されない。
新しいNPO→すぐには認定されない→寄付が集まらない→・・・・仮認定という考え方
まず、仮認定してから寄付を集めやすくし、それから本認定という形をとれるようになれば立ち上げたすぐのNPO法人も寄付を集めやすくなるのではないか?
今までは国税局が認定していたが、地域で認定できるようになることが大切ではないか?
公益法人→6か月かかるものを3-4カ月で認定できるようにする。
以上のようなことを考えている。
質問
佐藤氏
認定NPO法人、公益法人に寄付した時のメリットは?
大串氏
今までは所得控除
所得控除は所得の高い人ほど有利になった。
税額控除に変えることができないか?と議論している。
沢山の人が寄付してくれるようにするため、すそ野を広げたい。
山口氏
日本人はなるべく税金を払いたくないと思っている。
税金の控除をすることによって税収が落ちるのではないか?借金が増えることをどう考えるか?
大串氏
税収に対してマイナスになるが、公の仕事をみんなでしていくことで行政がしているしごとをNPOがするか、行政がするか選べるようになる。
そのことで財政的にはニュートラルになって欲しいと望む。
日本はギリシアに近い。行政がしていることで無駄になっていることをNPOがすることで有効なことになればいい。
古川氏
ふるさと納税が3年目になった。これは税額控除である。佐賀県は実額全国で20位くらいだが、人口を考慮するとかなりの額だといえる。大口の寄付も多い。
たとえば3,500万円とか1,000万円とか。
個人と社会の関係を考える税制。
自分が考えるものに支払う。税金も選べるようになる。
税収が減るのは意味のあること。無駄を減らそうとするのではないか?
報告があったりと信頼できる所にお金を出す。
例えば、
海外で災害があった時、佐賀県では見舞金を出すようにしている。
今までは日赤を通して寄付をしていた。
しかし、何に使われているか分からないので今度はユニセフに寄付した。
それでも何に使われているか分からなかった。
その次はフィリピンだったこともあり、地球市民の会に寄付した。
地球市民の会は佐賀県が出した見舞金を何の事業に使い、何ができたのかという報告書を出してくれた。
こうしたことをしたのは地球市民の会だけだった。
寄付を受けたからにはNPOにも報告責任があると思う。
テーマ3 「道州制と地方分権、地方主権」とNPOが果たすべき役割
道州制と地方分権、地方主権って違うの?一緒ではないの?国が地方に自分たちのことは自分たちで決めさせようってことなんでしょ?
大串氏
地域主権戦略会議を原口大臣を中心として考えている。
日本は中央集権。今までは機能していたが、現在は地元のことは地元で決めていくことという原則があって、補完性の原則がある。
コミュニティーで決められるものはコミュニティーで決める。
↓
コミュニティーで決められないことは市町、
↓
市町で決められないことは県、
↓
県で決められないことは国
↓
国に残ることは外交などだけになる。
近い人が決めていく。地元が権限を持っていく。
23年度は補助金を一括で地方へ交付し地方で何に使うか決めてもらう。
その受け皿は何が良いのか、道州制or県
地域主権を考えて、行動していくとだんだんと適正な規模が分かるのではないか?
大切なのは私たちが決められるということ。
税の納め先も、何に使うかも選べることも大切。
質問
佐藤氏
・管大臣は地域主権を進めているが、平成の大合併に反するのではないか?
・ミャンマーの子どもたちにひかれるのはなぜか?かわいそうだけではない。先祖や親を敬う気持ちを持っているからだ。そこが美しい。それに祈りがある。NPOの在り方もそこにあるのではないか?
・「農」を基本に学ぶ必要があるのではないか?
大串氏
小規模分散、平成の大合併。もう少し見ていかないと正確な答えは出ないのではないか?
小規模分散は自然の摂理、補完の原則。どの行政でどのくらいの大きさが必要か?これから分かってくるのではないか?
必要な財源、権限を地域の移譲していくことで分かるのではないか?
ベンチャーの人々で成功している人の話を聞くとデジタル的なことよりもアナログ的なこと、熱意や想いが大切だと言っている。
NPOでなければ背負えないものは熱さ、情念。これは行政では無理。
山口氏
大規模災害が起こる可能性が日本にはある。
関東大震災、富士山の噴火、東海地震、こういったことが起こると日本すべてがダメになる。
その前に独立した方が良いのではないか?
九州規模の独立国家だってある(デンマークやスイスなど)
九州自身が力をつけていくことが大切。ドミノ倒しにならないように。
大串氏
権限、財源が地域に戻されるとおさまりの良い規模になる。
それは道路、通信の規模だと思う。
古川氏
道州制・・・良いんじゃない?
でも下手をすると国家による地域分割になる可能性もある。
明治より日本は合併を繰り返している。しかし、県だけは変わっていない。
今のままでいいという理屈がわからない。
特区を国に訴えても通らない。権限よりも欲しいもの、それは責任。
県だけでは難しいことも、九州くらいなら出来ることもある。
目に見えるところでの節約やお金を出すことはできても、見えないものだと納得できない。
日本は超高齢者社会だが、ノルウェー、スウェーデン並みの消費税の税率は出来ない。
それは決める機関があまりにも遠すぎて見えないから。
ノルウェー、スウェーデンの人口だからこそ近くで決められていることが見えるので納得できている。
佐賀は道州制を引っ張って行っている。
議論の中心になって行かないといけない。九州モデルは佐賀県が作った。それが国のモデルになっている。
甲子園で応援するくらいの規模が妥当ではないか?((笑))
基礎自治体への財政と権限の移譲から始まっていくのではないか?
質問
(東京からの参加者)
税の控除は確定申告or年末調整?
出来れば年末調整にして欲しいのだか。
大串氏
日本は分かりずらい。アメリカは全員が確定申告をしなければならない。
今の日本のインフラでできるのは年末調整だと思う。調整改革が必要。
(熊本からの参加者)
税金の説明
年収300万円の人が12,000円の会費(寄付)を支払うとする
税金を10%とすると300万円×10%=30万円
認定NPO法人以外だと12,000円払っても何の税の控除はない。
これが認定NPO法人になると(税額控除)
300万円-12,000円=298万8千円
298万8千円×10%=29万8千円
30万円-29万8千円=1,200円
1,200円が税金から控除される。税金として支払うのは29万8千円
もし、税金分の30万円を寄付したとする
300万円×10%=30万円
寄付した金額の50%が控除されるので
15万円を税金として払うことになる。
もしこれが所得控除なら
300万円-30万円=270万円
270万円×10%=27万円
税金として27万円支払うことになる。
30万円は寄付しているので最終的には
税額控除では45万円(寄付+税金)
所得控除では57万円(寄付+税金)支払うこととなる。
最後に
山口氏
政治家でも行政マンではなくNPOが税金について半分でも使い道を考えられつようになることが新しい公共になるのではないか?
古川氏
程よい政府を目指すには協働をしていかなくてはいけない。
協働化テストはコスト削減ではなく県民満足度の向上が目的。
何でも小さくすることが良いとは思わない。
我々がしなければならないことをすべき。減らすことだけを目的としてはいけない。
協働機関の設置。(国会で原口大臣が提案している)
合併しなくても合併の効果を上げるもの
大串氏
共有したいもの、それは国民一人一人が自分たちで選択する時代になってきているということ。
国、県が何をしてくれるか?ではなく、自分自身が何をすべきか。を考えるべき。
NPOがそれを担っている。
私たちは何ができるのかという思いを拡げていかなくてはいけない。
Posted by On y Va! at 13:45│Comments(0)
│お勉強