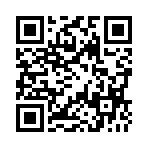志賀克洋氏有田学講演会@小路庵
2012年03月13日
昨日、女性懇話会さんが主宰されたまちづくり勉強会の内容です。
くがフィルターがかかっているのであしからず・・・
有田学 志賀克洋先生 @小路庵 3月12日18:40~21:30
地域づくりは自分たちが行うもの。日常の生活を行いつつ、行うことが地域づくりである。講師の話を聞いているだけでできるのであれば全国の地域は良くなっているはず。ではだれが悪いのか?それは地域の人。地域の人が実行しなければ解決しない。
行政、大型企業が来たからと言って町が良くなるわけではない。内発型地域振興。そういったものを行っていく人が増えていく事で有田が変わっていく。今までの5回で出してきた企画書などを有田に落とし込み、有田で行うことで有田は変わっていくだろう。
上杉鷹山の話。彼は250年前の米沢藩で地域づくりはほとんど行っている。ということは地域づくりについてほとんど成長していないということだ。農業の6次産業も彼が始めた(養蚕業→反物作り、ベニバナ→口紅、ゆでもち→峠で売るなど)藩校教育に力を入れた。
有田学は有田ならではのものを作っていかなければならい。
地域に必要とされる企業、団体であれば地域も残る事ができる。地域がなければ団体も企業も残らない。
旬の時期に旬のものをその場で売る。これが日本的。売ればもうかる、ではない。ネットで販売すれば簡単だが、そんなことをしても意味がない。その場に来てもらうことで商品以外のものを売る事ができる。それが地域の矜持である。
日本は20年来成長していない。文化による町づくり→文化で飯は食えないと言われた。しかしこれからは文化でしか飯は食えない。福祉、文化、農業が大切。農業をないがしろにしている国は良い国ではない。農業が全てのキーを握っている。共に食べ、美味しいを共有していく事が地域を繋げていくこと。
サッチャー、レーガン、小泉が始めたお金をもうけている人がもっと儲かる事で底辺が上がるという考え方だが、これは違う。お金を持っている人は選挙にも力を持っていく。選挙に関係のない力のない人のことを無視されるようになる。TPPの問題。これも農業だけの問題ではない。
竹田は高齢者率日本一になった。高齢者の人は将来が不安でお金を使わない。高齢者という購買層が減ることはない。イオンの3本柱アジア、◎◎(聞きとれなかった)、シニア。デパート、スーパーでは業績を落としているが、小売業で業績が落ちていない業種はコンビニだけ。コンビニは社会にとって必要な社会資本と言う考え方をしている。商品を売るのではなくサービスを売っている。
商店街が地域の中心であるべき。生活必需品を買うことができる、人が集まる。これを今コンビニが担っている。地域になって欠かせない店になっている。コンビニに頼っていてはいけない。商店街が担わなければならない。しかし、ここまで来るとコンビニと手を組むしかないようになってきているのではないか?
2010年日蘭交流400年記念フォーラムで駐日オランダ大使が「伊万里」の話をされている。
高齢者仕様のやきものが必要になるのではないか?ニーズがあるはず。値段の競争をしなければならないようなものは日本では無理ではないか?
「核家族から単家族へ」匠雅音著
竹田の岡城築城800年祭の事例
天守閣を作る。20日間だけ作る許可が下りた。20日でさらに戻すという限定。分厚いゴムシートを張り、コンクリートを打って作った。瓦は発砲スチロールで作った。しかし、式典、神事を必ず行った。そのたびにテレビなどで取り上げてもらった。3000万以上かかったが、市役所は400万しか出せなかった。翌日が落成式の日に台風が来た。宮大工さんが神楽舞などを舞った。そのおかげか知らないが、台風の被害は瓦が一枚飛んだだけだった。足りないお金はグッズを売って作った。それで1000万円は稼いだ。しかし足りないものはいろんな機会でうった。
キチンとした理想や理念がないと地域のためにならない。そういったものを理解できない首長がいないと難しい。ただし、若い人にそれが引きついでいく限りは失敗ではない。
地場の素材を使って物を作ろうということがいい。まず、作らないといけない。そうしなければ先に進まない。地域の産物はどこかに持っていく、どこかに送ろうということの繰り返しで育っていく。みんなで育てていくしかない。
イベントをするだけでは意味がない。人口が増えていくようなことをしなければ地域は作れない。
東日本大震災はもしかしたら戦後何十年間かで本来ならば作ってはいけないような潟、浜辺に住宅地や工場を作ったのではないか?潰れてしまったところは自然として残していく事の方が安心なのではないか?メモリアルパークなど。自然に対して謙虚な町づくり。利根川は河川工事をすればするほど災害被害額が大きくなっていく。経済成長の間違い。ナイル川の氾濫。加藤清正の灌漑。単に防波壁を作ればいいというものではない。
周辺地域から暮らしやすい中心地に人が集まっていくということを考えなければいけない。商店街のコミュニティ共同体を形成するということも考えなければならない。周辺からの移動。どうしても不便なところに住みたいと言う人は仕方がないが、そうではない人に対しては流入してもらい、中心商店街のコミュニティを形成していく事も真剣に考えなければならない。これは行政も考えること。
守らなければならいもの、信条を通さなければならないものには命をかけても行わなければならないのに、まちづくりにはそれができていない。だからまちづくりは甘い。簡単に諦めてはいけない。米の歴史には身代潰して水路を作ったり、木を植えたりしていた。木を植え、半世紀かけて水を呼んだ。そういった歴史に感謝しなければならない。簡単に諦めてはいけない。すぐには結果は出ない。
ユートピア=no where w=私たち 私達が動くことで now here=今ここに
私達が動けば何もないところが、ユートピアになる。
地域鎖国。エネルギー、水、食料の調達←地元のものでまかなえるようにする。
国に期待しても何もしてはくれない。末端市町村は国からも県からも言われて辛い。県は国から来た資料をそのままコピーして市町に持っていくだけ。(そうか??私が知っている佐賀県の職員さんのほとんどはすごくできる人が多いと思うけど・・・大分県は違うの??)
知恵を出し合い、地域で自衛していかなければならない。そのために商店街で地元のものが買えるようにしなければならない。
戦略と戦術は違う。戦略はプラン、戦術はツール。そして必要なのは戦闘員が必要。軌道修正しながら行っていく事が地域活性化である。
原田議員より報告(松尾佳昭さんが調べたもの)
学校給食の去年の4月から1月までの野菜の地元産の割合
玉ねぎ町内産6割 葉物野菜は伊万里産まで加えるとほとんどがまかなっている。
米は作付は2割減り、収穫量は1割減っている。
2条大麦、米、玉ねぎ、高菜が主要産品
高くても地場のものを買うことが地域を育てることにつながる。
くがフィルターがかかっているのであしからず・・・
有田学 志賀克洋先生 @小路庵 3月12日18:40~21:30
地域づくりは自分たちが行うもの。日常の生活を行いつつ、行うことが地域づくりである。講師の話を聞いているだけでできるのであれば全国の地域は良くなっているはず。ではだれが悪いのか?それは地域の人。地域の人が実行しなければ解決しない。
行政、大型企業が来たからと言って町が良くなるわけではない。内発型地域振興。そういったものを行っていく人が増えていく事で有田が変わっていく。今までの5回で出してきた企画書などを有田に落とし込み、有田で行うことで有田は変わっていくだろう。
上杉鷹山の話。彼は250年前の米沢藩で地域づくりはほとんど行っている。ということは地域づくりについてほとんど成長していないということだ。農業の6次産業も彼が始めた(養蚕業→反物作り、ベニバナ→口紅、ゆでもち→峠で売るなど)藩校教育に力を入れた。
有田学は有田ならではのものを作っていかなければならい。
地域に必要とされる企業、団体であれば地域も残る事ができる。地域がなければ団体も企業も残らない。
旬の時期に旬のものをその場で売る。これが日本的。売ればもうかる、ではない。ネットで販売すれば簡単だが、そんなことをしても意味がない。その場に来てもらうことで商品以外のものを売る事ができる。それが地域の矜持である。
日本は20年来成長していない。文化による町づくり→文化で飯は食えないと言われた。しかしこれからは文化でしか飯は食えない。福祉、文化、農業が大切。農業をないがしろにしている国は良い国ではない。農業が全てのキーを握っている。共に食べ、美味しいを共有していく事が地域を繋げていくこと。
サッチャー、レーガン、小泉が始めたお金をもうけている人がもっと儲かる事で底辺が上がるという考え方だが、これは違う。お金を持っている人は選挙にも力を持っていく。選挙に関係のない力のない人のことを無視されるようになる。TPPの問題。これも農業だけの問題ではない。
竹田は高齢者率日本一になった。高齢者の人は将来が不安でお金を使わない。高齢者という購買層が減ることはない。イオンの3本柱アジア、◎◎(聞きとれなかった)、シニア。デパート、スーパーでは業績を落としているが、小売業で業績が落ちていない業種はコンビニだけ。コンビニは社会にとって必要な社会資本と言う考え方をしている。商品を売るのではなくサービスを売っている。
商店街が地域の中心であるべき。生活必需品を買うことができる、人が集まる。これを今コンビニが担っている。地域になって欠かせない店になっている。コンビニに頼っていてはいけない。商店街が担わなければならない。しかし、ここまで来るとコンビニと手を組むしかないようになってきているのではないか?
2010年日蘭交流400年記念フォーラムで駐日オランダ大使が「伊万里」の話をされている。
高齢者仕様のやきものが必要になるのではないか?ニーズがあるはず。値段の競争をしなければならないようなものは日本では無理ではないか?
「核家族から単家族へ」匠雅音著
竹田の岡城築城800年祭の事例
天守閣を作る。20日間だけ作る許可が下りた。20日でさらに戻すという限定。分厚いゴムシートを張り、コンクリートを打って作った。瓦は発砲スチロールで作った。しかし、式典、神事を必ず行った。そのたびにテレビなどで取り上げてもらった。3000万以上かかったが、市役所は400万しか出せなかった。翌日が落成式の日に台風が来た。宮大工さんが神楽舞などを舞った。そのおかげか知らないが、台風の被害は瓦が一枚飛んだだけだった。足りないお金はグッズを売って作った。それで1000万円は稼いだ。しかし足りないものはいろんな機会でうった。
キチンとした理想や理念がないと地域のためにならない。そういったものを理解できない首長がいないと難しい。ただし、若い人にそれが引きついでいく限りは失敗ではない。
地場の素材を使って物を作ろうということがいい。まず、作らないといけない。そうしなければ先に進まない。地域の産物はどこかに持っていく、どこかに送ろうということの繰り返しで育っていく。みんなで育てていくしかない。
イベントをするだけでは意味がない。人口が増えていくようなことをしなければ地域は作れない。
東日本大震災はもしかしたら戦後何十年間かで本来ならば作ってはいけないような潟、浜辺に住宅地や工場を作ったのではないか?潰れてしまったところは自然として残していく事の方が安心なのではないか?メモリアルパークなど。自然に対して謙虚な町づくり。利根川は河川工事をすればするほど災害被害額が大きくなっていく。経済成長の間違い。ナイル川の氾濫。加藤清正の灌漑。単に防波壁を作ればいいというものではない。
周辺地域から暮らしやすい中心地に人が集まっていくということを考えなければいけない。商店街のコミュニティ共同体を形成するということも考えなければならない。周辺からの移動。どうしても不便なところに住みたいと言う人は仕方がないが、そうではない人に対しては流入してもらい、中心商店街のコミュニティを形成していく事も真剣に考えなければならない。これは行政も考えること。
守らなければならいもの、信条を通さなければならないものには命をかけても行わなければならないのに、まちづくりにはそれができていない。だからまちづくりは甘い。簡単に諦めてはいけない。米の歴史には身代潰して水路を作ったり、木を植えたりしていた。木を植え、半世紀かけて水を呼んだ。そういった歴史に感謝しなければならない。簡単に諦めてはいけない。すぐには結果は出ない。
ユートピア=no where w=私たち 私達が動くことで now here=今ここに
私達が動けば何もないところが、ユートピアになる。
地域鎖国。エネルギー、水、食料の調達←地元のものでまかなえるようにする。
国に期待しても何もしてはくれない。末端市町村は国からも県からも言われて辛い。県は国から来た資料をそのままコピーして市町に持っていくだけ。(そうか??私が知っている佐賀県の職員さんのほとんどはすごくできる人が多いと思うけど・・・大分県は違うの??)
知恵を出し合い、地域で自衛していかなければならない。そのために商店街で地元のものが買えるようにしなければならない。
戦略と戦術は違う。戦略はプラン、戦術はツール。そして必要なのは戦闘員が必要。軌道修正しながら行っていく事が地域活性化である。
原田議員より報告(松尾佳昭さんが調べたもの)
学校給食の去年の4月から1月までの野菜の地元産の割合
玉ねぎ町内産6割 葉物野菜は伊万里産まで加えるとほとんどがまかなっている。
米は作付は2割減り、収穫量は1割減っている。
2条大麦、米、玉ねぎ、高菜が主要産品
高くても地場のものを買うことが地域を育てることにつながる。
Posted by On y Va! at 13:05│Comments(0)
│CSO