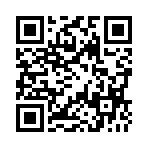小城市市民協働研修会
2010年01月29日


小城市で行われている「市民協働研修会」に参加してきました。
小城市民、行政職員に対しての研修会だったのですが、
私自身、これから「協働」が中間支援の核になるのではないか?と思っています。
それもあり、ずうずうしくも研修会に参加させてもらいました。

今回の講師のは特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構の代表川副知子さん
私達の大先輩ということさえもおこがましい方です。
佐賀県各地域の事例を交えながらのお話は分かりやすく、なるほど!と納得するものでした。
そしてやはり仰っていたのが、
「協働は手段であって、目的ではない!!」
協働のための事業ではなく、より良い結果を残すために協働というツールを使うんだ!
ということですよね。
たとえば・・・・
ある町の老人組織がネットワーク化されないのは
今までが町のイベントにボランティアという名の動員を行政からかけられていたから。
自主的な団体を作って行政のネットワークに参加すると
また動員やボランティアと言いながらも強制的なことをさせられるのではないか?
と疑っているから。

行政には行政本来の仕事をしてもらうために、協働は行うべき。
そのためにはコミュニケーションを持ってお互いに信頼関係を持つことが大切。
1+1=2では協働を行う意味がない!!1+1>2
有田の活性化について
以前の有田には陶器市以外では人通りがなかった。(確かに・・・)
市民団体+商店+行政が一体となって世の中のニーズを掴んできた。
季節ごとに春→雛祭りの陶磁器祭り
夏→蛍をみにきん祭、高校生のウィンドディスプレイコンテスト
秋→秋の陶磁器祭
企画は民間が行い、
行政がうまくPR活動を行っている。
→これは県内の成功事例だと言える
有田町、褒められちゃいましたね。
でも、有田町もまだまだだと思います。
協働に対する指針もまだありませんし、CSOがしんどいだけ・・・・みたいなことを防ぐためにはどんなことを取りきめなければいけないのか?
まだまだ課題は多いです。

最後にグループワークを行いました。
目標をたて、それを実現するためにはどんなことを行っていかなければいけないのか?
というのをゴールから逆算していく・・・というものでした。
突拍子もない意見が出ましたが、それも、ワークの面白いところ。
その突拍子のない意見をどう生かすか?
行政と市民団体のこれからの課題かもしれませんね。
李参平の絵本発行
2010年01月26日
陶都有田青年会議所さんが絵本を発行されました。
有田偉人ものがたりその一
李参平
この本は昨年の12月21日に発行されました。
企画・編集は社団法人陶都有田青年会議所
イラスト・タイトルデザインは陶祖李参平窯の金ヶ江美里さん

可愛い絵ですよね。
実は絵を描いている金ヶ江さんとは知り合いなので
彼女が作画しているときから見ていたので
なんだか不思議な感じです。

この本は子どもたちに有田の町を誇りに思ってもらいたいという思いから作られました。
その二、その三とこれからも続けていく予定だそうです。
詳しいことは陶都有田青年会議所までご連絡ください。
有田町大樽1-4-1 有田商工会議所1階
電話0955-42-2097
有田偉人ものがたりその一
李参平
この本は昨年の12月21日に発行されました。
企画・編集は社団法人陶都有田青年会議所
イラスト・タイトルデザインは陶祖李参平窯の金ヶ江美里さん

可愛い絵ですよね。
実は絵を描いている金ヶ江さんとは知り合いなので
彼女が作画しているときから見ていたので
なんだか不思議な感じです。

この本は子どもたちに有田の町を誇りに思ってもらいたいという思いから作られました。
その二、その三とこれからも続けていく予定だそうです。
詳しいことは陶都有田青年会議所までご連絡ください。
有田町大樽1-4-1 有田商工会議所1階
電話0955-42-2097
理事会
2010年01月25日
有田町どっとこむの理事会が1月25日にありました。
理事会は理事のための会なので私は参加できないのですが、
内部のことも学んだほうがいいということで特別にオブザーバーとして参加させてもらっています。
内容についてはここでは書けませんが、
NPOとは、理事とは、まちづくりとは、熱い想いを学ばさせていただいています。
町のためと団体の運営。
お互いがいい方向で進むことができればいいのですが、
これも、最近真剣に考えている協働とは?に行きつく気がします。
協働の意義、まだ、自分の言葉で語ることができません。
他の方が沢山意義を伝えてくださいますが、まだ、自分の言葉になっていない気がします。
でも分かるのは決して「労働ダンピング」ではないことだけは私の言葉で言えます!!
そして、
まちをつくっていくということ。
オンパクの研修でも思いましたが、熱い想いを継続し続ける難しさとかっこよさ。
パッション、ミッション、そして最後はやはりテンション。
(坂本達さんの言葉)
テンション上げて行きましょう!!
理事会は理事のための会なので私は参加できないのですが、
内部のことも学んだほうがいいということで特別にオブザーバーとして参加させてもらっています。
内容についてはここでは書けませんが、
NPOとは、理事とは、まちづくりとは、熱い想いを学ばさせていただいています。
町のためと団体の運営。
お互いがいい方向で進むことができればいいのですが、
これも、最近真剣に考えている協働とは?に行きつく気がします。
協働の意義、まだ、自分の言葉で語ることができません。
他の方が沢山意義を伝えてくださいますが、まだ、自分の言葉になっていない気がします。
でも分かるのは決して「労働ダンピング」ではないことだけは私の言葉で言えます!!
そして、
まちをつくっていくということ。
オンパクの研修でも思いましたが、熱い想いを継続し続ける難しさとかっこよさ。
パッション、ミッション、そして最後はやはりテンション。
(坂本達さんの言葉)
テンション上げて行きましょう!!
オンパク研修会参加
2010年01月22日
プライベートでオンパク研修会に参加してきました。

別府ではオンパクというまちづくりが行われています。
川北秀人氏が講師として参加れています。
まぁ、川北氏の追っかけです(笑)

特定非営利活動法人 ハットウ・オンパクの野上さん。
とても熱い気持ちを持ってまちづくりを行われています。
「まちづくり」する人はは変わった人
のどちらか。
何もしない、自分のまちを卑下する人
オンパクを行ったこと、オンパクを含む別府のまちづくりで別府は変わったこと
↓ ↓ ↓
・「まちへの愛着」を語る人が増えた
・チャレンジする人が増えた
オンパク、地域づくりで変わったもの
↓
ひとが変わった!!
「まち歩き」から始まった「まち活かし」
長崎さるくも田上市長が観光課時代にたまたま新聞で別府のオンパクが取り上げられていたことから始まった。
それから田上市長は別府オンパクに通いつめて「長崎さるく」を始めた。
観光とまちおこし・まち活かしのせめぎあいはある。
観光がメインだと毎日何かしらのエンターテイメントが必要となる。
まちおこしがメインだと自分たちができる範囲、期間で行ってよい。
変わっている人がするまちづくりから普通の人がするまちづくりへ
地域は魅力であふれている
地元の人でさえ知らない。
頑張る人が沢山いる
場が与えられていないだけ
主役になると人は変わる
小さく成功した体験の積み重ねが自信になっていく。
地域の人が自らする
外からの人が集客システムを持ってきてするのではなく、続けるために地域の人が行うこと。
他所の人がその町に住みついてくれたらOK!
オンパクのアプローチ
ただひたすら「さるく」
変なもの、格調高いもの、雑多なもの、まちにはいろんなものが溢れている。
それがプログラムになっていく。
体験型→まちはネタの宝庫。地元の人が知らないことを発掘して紹介すること!
オンパクの数字
地域会員→オンパクファンクラブ6021人
オンパクプログラム参加者35260人
パートナー→自らプログラムを考え、運営する人80名
サポーター→パートナーを支える人・団体55団体
パートナーとサポーターが一緒になって128のプログラムを提供
協力企業→告知、ガイドブック配布10企業
メディア15企業
スポンサー→16団体

こちらは特定非営利活動法人吉備野工房ちみちの加藤せい子理事長
サカキバラ事件後、大人がちゃんと生きていることを子どもに見せなければならないとまちづくりを始める。
県や行政の人は有給で守られた環境で仕事をしている。
自分はボランティアで同じような仕事を彼ら以上に働いている
自分の力をお金で測ってみたいとと持っていた時にハットウ・オンパクの鶴田さん、野上さん、IIHEOの川北さんと出会った。
男女差で悔しい想いもした!!
地域には人も物も点在している。
それをつなげるために中間支援組織を作った。
まちをつくるということ。
地域を知ること。
ステキな人、ステキな場所はある。そのイメージを変えること。
使い古されたイメージは使わない。
みんな背中を押してくれる人を待っている。何かしたい!と思っている。
総社版オンパク「みちくさ小道」
海外からの「ちみち」の研修を受け入れたことでパートナーのテンションが上がった。
パートナーが成長する→プログラムの進化
オンパクプログラムはインキュベーション、商いトライアル、Iターンの可能性を秘めている

こちらのさわやか青年は「都城まちづくり株式会社」の佐土原太志さん
都城版オンパクである「ボンパク」(盆地泊覧会)は宮崎県だけでなく、同じ文化圏の鹿児島県の一部もエリアにしています。
リスクを取ることに慣れていない人がチャレンジすることをサポートすることがボンパク!!
佐土原さんのお話を聞きたかったのですが、
残念なことに同じ時間にラジオ出演が重なってしまいました。
いつもの「有田ドイツ学通信」です。
なんか、昨日に限って調子に乗ってしまい、普段なら5分程度のコーナーが20分もしゃべっていました(笑)
ということでほとんど佐土原さんのお話は聞けませんでした。
多分、一緒に参加した武雄のよもぎさんや小城のメイラクさん、呼子の呼子お助けさんが報告してくれるかな?
まだまだ、報告したいことはありますが、それはまた明日にでも・・・・

別府ではオンパクというまちづくりが行われています。
川北秀人氏が講師として参加れています。
まぁ、川北氏の追っかけです(笑)

特定非営利活動法人 ハットウ・オンパクの野上さん。
とても熱い気持ちを持ってまちづくりを行われています。
「まちづくり」する人はは変わった人
のどちらか。
何もしない、自分のまちを卑下する人
オンパクを行ったこと、オンパクを含む別府のまちづくりで別府は変わったこと
↓ ↓ ↓
・「まちへの愛着」を語る人が増えた
・チャレンジする人が増えた
オンパク、地域づくりで変わったもの
↓
ひとが変わった!!
「まち歩き」から始まった「まち活かし」
長崎さるくも田上市長が観光課時代にたまたま新聞で別府のオンパクが取り上げられていたことから始まった。
それから田上市長は別府オンパクに通いつめて「長崎さるく」を始めた。
観光とまちおこし・まち活かしのせめぎあいはある。
観光がメインだと毎日何かしらのエンターテイメントが必要となる。
まちおこしがメインだと自分たちができる範囲、期間で行ってよい。
変わっている人がするまちづくりから普通の人がするまちづくりへ
地域は魅力であふれている
地元の人でさえ知らない。
頑張る人が沢山いる
場が与えられていないだけ
主役になると人は変わる
小さく成功した体験の積み重ねが自信になっていく。
地域の人が自らする
外からの人が集客システムを持ってきてするのではなく、続けるために地域の人が行うこと。
他所の人がその町に住みついてくれたらOK!
オンパクのアプローチ
ただひたすら「さるく」
変なもの、格調高いもの、雑多なもの、まちにはいろんなものが溢れている。
それがプログラムになっていく。
体験型→まちはネタの宝庫。地元の人が知らないことを発掘して紹介すること!
オンパクの数字
地域会員→オンパクファンクラブ6021人
オンパクプログラム参加者35260人
パートナー→自らプログラムを考え、運営する人80名
サポーター→パートナーを支える人・団体55団体
パートナーとサポーターが一緒になって128のプログラムを提供
協力企業→告知、ガイドブック配布10企業
メディア15企業
スポンサー→16団体

こちらは特定非営利活動法人吉備野工房ちみちの加藤せい子理事長
サカキバラ事件後、大人がちゃんと生きていることを子どもに見せなければならないとまちづくりを始める。
県や行政の人は有給で守られた環境で仕事をしている。
自分はボランティアで同じような仕事を彼ら以上に働いている
自分の力をお金で測ってみたいとと持っていた時にハットウ・オンパクの鶴田さん、野上さん、IIHEOの川北さんと出会った。
男女差で悔しい想いもした!!
地域には人も物も点在している。
それをつなげるために中間支援組織を作った。
まちをつくるということ。
地域を知ること。
ステキな人、ステキな場所はある。そのイメージを変えること。
使い古されたイメージは使わない。
みんな背中を押してくれる人を待っている。何かしたい!と思っている。
総社版オンパク「みちくさ小道」
海外からの「ちみち」の研修を受け入れたことでパートナーのテンションが上がった。
パートナーが成長する→プログラムの進化
オンパクプログラムはインキュベーション、商いトライアル、Iターンの可能性を秘めている

こちらのさわやか青年は「都城まちづくり株式会社」の佐土原太志さん
都城版オンパクである「ボンパク」(盆地泊覧会)は宮崎県だけでなく、同じ文化圏の鹿児島県の一部もエリアにしています。
リスクを取ることに慣れていない人がチャレンジすることをサポートすることがボンパク!!
佐土原さんのお話を聞きたかったのですが、
残念なことに同じ時間にラジオ出演が重なってしまいました。
いつもの「有田ドイツ学通信」です。
なんか、昨日に限って調子に乗ってしまい、普段なら5分程度のコーナーが20分もしゃべっていました(笑)
ということでほとんど佐土原さんのお話は聞けませんでした。
多分、一緒に参加した武雄のよもぎさんや小城のメイラクさん、呼子の呼子お助けさんが報告してくれるかな?
まだまだ、報告したいことはありますが、それはまた明日にでも・・・・
有田町どっとこむニュースVol.4
2010年01月19日
昨日のブログでもご紹介しましたが、
やっと今月分の広報誌をお披露目できるようになりました。
広報誌は「ひととひと」そして「お金」をつなげてくれる有効なツールだと思います。
自分たちがいくら良いことをしていてもそれを周りの方に分かってもらえなければ良いことしていていも認めてもらえませんよね。
良いことをしていれば、いつか分かってもらえる。
だから、活動をしていこう!そのうち分かってもらえる・・・・
多分、これではいつになっても認めてもらえないと思います。
自分から「私達はこんなことをしています!」と言えなければいけませんね。
そのために広報誌(ニューズレター)を作成し、自分たちの活動を冷静に見る必要もあるでしょう。
広報誌を印刷するにはお金がかかります。
お金がない団体はできないじゃないか!
そう言われる方のために、この「ブログ」が活躍します。
広報誌よりも手軽に、即時的に、しかも無料でPRすることができます。
と言いつつも、紙媒体も重要ですよね。
紙媒体の広報誌と、ICT(インフォメーション&コニュミケーション テクノロジー)を利用した広報活動。
両方できることが一番だと思います。
私はまだ、紙媒体で精いっぱいです。
まずは理事による新年のあいさつ

イベント情報などのお知らせと中間支援組織べんじゃら広場について

イベント情報!
ICT利活用講座のチラシです。
基山のサポーター、アーキーさんが作ってくださったものを転用させてもらいました・・・

今まで別々に発行していた学童保育の「べんじゃらきっずNEWS」を今回からは一緒に発行します。
べんじゃらきっずの先生に作ってもらいました!
本当はこの間に棚田保全協議会の広報誌「グリーンスマイル」が入ります。
こちらの方は棚田保全協議会のブログで紹介があると思いますので、ここでは割愛します!とこのブログを使ってブログ更新のプレッシャーをかけてみたり(笑)

最後のページは前回のイベント情報で紹介しました
佐賀IYEOさんとのコラボイベントの報告と観光部門の紹介、そして有田町どっとこむの会員募集のお知らせです。
最後は各部門のブログとホームページの紹介です!

実際に私が書いた文章はそんなに多くありません。
それに、この広報誌はテンプレート(雛形)を使って作っていますので
本当に文章を写真を指示された場所に貼り付けていくだけです。
書いてもらったこと、このブログで書いたこと、それらのことをコピー&ペーストしていくだけです。
こんなこと書くと手軽に広報誌ができるような気がするでしょ!
実際にそうなんですよ。
気張らずに、自分の出来る範囲内で、身の丈にあった広報誌を作りましょう。
私も出来るだけ毎月、発行できるように、「身の丈広報誌」を発行していきます。
もちろん、ブログも更新ですね。
やっと今月分の広報誌をお披露目できるようになりました。
広報誌は「ひととひと」そして「お金」をつなげてくれる有効なツールだと思います。
自分たちがいくら良いことをしていてもそれを周りの方に分かってもらえなければ良いことしていていも認めてもらえませんよね。
良いことをしていれば、いつか分かってもらえる。
だから、活動をしていこう!そのうち分かってもらえる・・・・
多分、これではいつになっても認めてもらえないと思います。
自分から「私達はこんなことをしています!」と言えなければいけませんね。
そのために広報誌(ニューズレター)を作成し、自分たちの活動を冷静に見る必要もあるでしょう。
広報誌を印刷するにはお金がかかります。
お金がない団体はできないじゃないか!
そう言われる方のために、この「ブログ」が活躍します。
広報誌よりも手軽に、即時的に、しかも無料でPRすることができます。
と言いつつも、紙媒体も重要ですよね。
紙媒体の広報誌と、ICT(インフォメーション&コニュミケーション テクノロジー)を利用した広報活動。
両方できることが一番だと思います。
私はまだ、紙媒体で精いっぱいです。
まずは理事による新年のあいさつ
イベント情報などのお知らせと中間支援組織べんじゃら広場について
イベント情報!
ICT利活用講座のチラシです。
基山のサポーター、アーキーさんが作ってくださったものを転用させてもらいました・・・

今まで別々に発行していた学童保育の「べんじゃらきっずNEWS」を今回からは一緒に発行します。
べんじゃらきっずの先生に作ってもらいました!
本当はこの間に棚田保全協議会の広報誌「グリーンスマイル」が入ります。
こちらの方は棚田保全協議会のブログで紹介があると思いますので、ここでは割愛します!とこのブログを使ってブログ更新のプレッシャーをかけてみたり(笑)
助成金情報!ご利用ください!
最後のページは前回のイベント情報で紹介しました
佐賀IYEOさんとのコラボイベントの報告と観光部門の紹介、そして有田町どっとこむの会員募集のお知らせです。
最後は各部門のブログとホームページの紹介です!
実際に私が書いた文章はそんなに多くありません。
それに、この広報誌はテンプレート(雛形)を使って作っていますので
本当に文章を写真を指示された場所に貼り付けていくだけです。
書いてもらったこと、このブログで書いたこと、それらのことをコピー&ペーストしていくだけです。
こんなこと書くと手軽に広報誌ができるような気がするでしょ!
実際にそうなんですよ。
気張らずに、自分の出来る範囲内で、身の丈にあった広報誌を作りましょう。
私も出来るだけ毎月、発行できるように、「身の丈広報誌」を発行していきます。
もちろん、ブログも更新ですね。
広報誌vol4
2010年01月18日
広報誌「有田町どっとこむニュース」のVol.4をやっと紹介できようになりました。
今回は盛りだくさんの内容です。
有田町どっとこむ理事からの新年のあいさつ、
イベント情報
中間支援組織「べんじゃら広場」について
学童保育「べんじゃらきっず」について
棚田部門「グリーンスマイル」
助成金情報
イベント報告
観光部門について
これだけの内容は読み応え有りますよ。
有田町どっとこむの会員さんにはもうお送りしましたが、
興味を持って下さった方にはお分けしますので、
どうぞ、ご連絡くださいね。
近々、県内のCSOサポートセンター、県庁やさが市民活動プラザにも置いてもらう予定です。
見かけたら、ご覧ください。
16日にはi-スクエアビル5階で
「ICT利活用講座」の講師をしてきました。
内容は「新規会員獲得と資金獲得につながるニューズレターと報告書」
平たく言えば「ひととおかねをつなげる広報誌と報告書」ですね。
広報誌を作ったからと言って簡単には会員が増えるわけでも寄付が集まるわけではありませんが、
自分たちが行っている活動をお知らせするためには必要です。
自己満足にならないためにもニューズレターと報告書は作った方がいいですね。
講師としてお話ししたからには、
「広報誌のおかげで会員さんが増えました!」
とご報告できるように頑張ります!!
ちなみに、他のメンバーの紹介です。
基山のアーキーさんは「あなたのイベントチラシに市民がクギづけ」→http://akira.sagafan.jp/t177509
武雄のよもぎさんは「人と人、地域と地域が繋がるサポーター獲得ブログの活用法」→http://csotakeo.sagafan.jp/t177444
今回は盛りだくさんの内容です。
有田町どっとこむ理事からの新年のあいさつ、
イベント情報
中間支援組織「べんじゃら広場」について
学童保育「べんじゃらきっず」について
棚田部門「グリーンスマイル」
助成金情報
イベント報告
観光部門について
これだけの内容は読み応え有りますよ。
有田町どっとこむの会員さんにはもうお送りしましたが、
興味を持って下さった方にはお分けしますので、
どうぞ、ご連絡くださいね。
近々、県内のCSOサポートセンター、県庁やさが市民活動プラザにも置いてもらう予定です。
見かけたら、ご覧ください。
16日にはi-スクエアビル5階で
「ICT利活用講座」の講師をしてきました。
内容は「新規会員獲得と資金獲得につながるニューズレターと報告書」
平たく言えば「ひととおかねをつなげる広報誌と報告書」ですね。
広報誌を作ったからと言って簡単には会員が増えるわけでも寄付が集まるわけではありませんが、
自分たちが行っている活動をお知らせするためには必要です。
自己満足にならないためにもニューズレターと報告書は作った方がいいですね。
講師としてお話ししたからには、
「広報誌のおかげで会員さんが増えました!」
とご報告できるように頑張ります!!
ちなみに、他のメンバーの紹介です。
基山のアーキーさんは「あなたのイベントチラシに市民がクギづけ」→http://akira.sagafan.jp/t177509
武雄のよもぎさんは「人と人、地域と地域が繋がるサポーター獲得ブログの活用法」→http://csotakeo.sagafan.jp/t177444
謹賀新年 今年もべんじゃら広場をよろしくお願いします
2010年01月04日
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
上は有田町どっとこむの年賀状です。
市民活動(中間)支援だけでなく棚田保全や学童保育、観光の写真も載せています。
こちらは私個人から。
今年も本当によろしくお願いします。