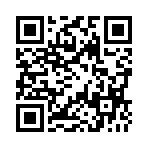小城市市民協働研修会
2010年01月29日


小城市で行われている「市民協働研修会」に参加してきました。
小城市民、行政職員に対しての研修会だったのですが、
私自身、これから「協働」が中間支援の核になるのではないか?と思っています。
それもあり、ずうずうしくも研修会に参加させてもらいました。

今回の講師のは特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構の代表川副知子さん
私達の大先輩ということさえもおこがましい方です。
佐賀県各地域の事例を交えながらのお話は分かりやすく、なるほど!と納得するものでした。
そしてやはり仰っていたのが、
「協働は手段であって、目的ではない!!」
協働のための事業ではなく、より良い結果を残すために協働というツールを使うんだ!
ということですよね。
たとえば・・・・
ある町の老人組織がネットワーク化されないのは
今までが町のイベントにボランティアという名の動員を行政からかけられていたから。
自主的な団体を作って行政のネットワークに参加すると
また動員やボランティアと言いながらも強制的なことをさせられるのではないか?
と疑っているから。

行政には行政本来の仕事をしてもらうために、協働は行うべき。
そのためにはコミュニケーションを持ってお互いに信頼関係を持つことが大切。
1+1=2では協働を行う意味がない!!1+1>2
有田の活性化について
以前の有田には陶器市以外では人通りがなかった。(確かに・・・)
市民団体+商店+行政が一体となって世の中のニーズを掴んできた。
季節ごとに春→雛祭りの陶磁器祭り
夏→蛍をみにきん祭、高校生のウィンドディスプレイコンテスト
秋→秋の陶磁器祭
企画は民間が行い、
行政がうまくPR活動を行っている。
→これは県内の成功事例だと言える
有田町、褒められちゃいましたね。
でも、有田町もまだまだだと思います。
協働に対する指針もまだありませんし、CSOがしんどいだけ・・・・みたいなことを防ぐためにはどんなことを取りきめなければいけないのか?
まだまだ課題は多いです。

最後にグループワークを行いました。
目標をたて、それを実現するためにはどんなことを行っていかなければいけないのか?
というのをゴールから逆算していく・・・というものでした。
突拍子もない意見が出ましたが、それも、ワークの面白いところ。
その突拍子のない意見をどう生かすか?
行政と市民団体のこれからの課題かもしれませんね。