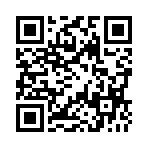伝統文化子ども教室1
2010年08月10日
文化庁主管の「伝統文化こども教室」の採択を受けて有田町どっとこむでは
べんじゃらきっずと一緒に「べんじゃらきっずおくんち教室」を今日から始めました。

有田の伝統でもあるおくんち。
以前に比べその規模も小さくなってきました。
もちろん子どもたちの参加も少なくなってしまい、おくんちに参加したことのない人たちも増えています。
実は私も先一昨年初めておくんちのパレードに参加しました(恥)
昔、有田のおくんちもけんか祭りだったそうです。
地区ごとに神輿を担ぎ、陶山神社を駆け登り、どの地区が一番早く登れたかを競っていたそうです。
この頃は有田の「上」と言われる地区のお祭りでした。
それが時代が進むにつれて、けんか祭りの要素は減っていきました。
有田の町自体が芸事を嗜むことが当たり前だったこともあり、一家に一棹(ひとさお)、三味線があったようです。
スピーカーもテープもCDもない時代は地区で三味線隊を作って、その曲に合わせて踊りを踊って回ったそうです。
この三味線隊。
若い女性が山車に乗って三味線を弾いていたとのこと。
なぜか分かりますか?
それは言葉は悪いですが、「お嫁さんの見本市」という側面もあったそうです。
今で言う「婚活」でしょうか?
というのも、商人さんは取引先のお客様を自宅でもてなしていました。
それは、焼物の使い方を実際にお客様にお見せし、つかって頂くため。
そのため有田の女性はお客様をもてなすため、お料理が上手、三味線や太鼓、唄、日舞が必須のようでした。
実際に有田には日舞の先生やお花の先生、三味線の先生、お謡いの先生などたくさんのいわゆる「趣味」の先生がたくさんいらっしゃいます。
昔の子どもたちは塾に通うように三味線や日舞を習いに行っていたそうです。
(私の親の時代はまだまだ多かったようです。)
有田皿山三味線隊のみなさんはそんな時代を知る方々。
でも「昔は三味線の音が響いて良かったね。」と昔を懐かしむだけではなく、
若い人にも有田の三味線文化を伝えたいという想いを持ってらっしゃいました。
一応、私も三味線隊の一員でもあるので(三味線は弾けませんが・・・・)その想いをどうにかして活かしたいと思い、今回子どもたちのおくんち教室を行うことにしたのです。
子ども時代に三味線や太鼓を体験することで、大人になってからは有田のおくんちに少しでも愛着を持ってくれたら、
大人になってからでいいので三味線や太鼓を又習ってみたいと思ってくれたら、
それより何より、有田を誇りに思ってくれるようにと三味線隊のみなさんと私たちは願っています。
今日は初めて三味線や太鼓に子どもたちが触れました。
子どもの体には三味線は大きくて重たい楽器です。
それでも一生懸命に練習してくれましたよ。
ほとんどの子供たちが「さくらさくら」のワンフレーズは弾けるようになりました。
おくんちで皆さんに披露しますので、楽しみにしておいてくださいね。




べんじゃらきっずと一緒に「べんじゃらきっずおくんち教室」を今日から始めました。

有田の伝統でもあるおくんち。
以前に比べその規模も小さくなってきました。
もちろん子どもたちの参加も少なくなってしまい、おくんちに参加したことのない人たちも増えています。
実は私も先一昨年初めておくんちのパレードに参加しました(恥)
昔、有田のおくんちもけんか祭りだったそうです。
地区ごとに神輿を担ぎ、陶山神社を駆け登り、どの地区が一番早く登れたかを競っていたそうです。
この頃は有田の「上」と言われる地区のお祭りでした。
それが時代が進むにつれて、けんか祭りの要素は減っていきました。
有田の町自体が芸事を嗜むことが当たり前だったこともあり、一家に一棹(ひとさお)、三味線があったようです。
スピーカーもテープもCDもない時代は地区で三味線隊を作って、その曲に合わせて踊りを踊って回ったそうです。
この三味線隊。
若い女性が山車に乗って三味線を弾いていたとのこと。
なぜか分かりますか?
それは言葉は悪いですが、「お嫁さんの見本市」という側面もあったそうです。
今で言う「婚活」でしょうか?
というのも、商人さんは取引先のお客様を自宅でもてなしていました。
それは、焼物の使い方を実際にお客様にお見せし、つかって頂くため。
そのため有田の女性はお客様をもてなすため、お料理が上手、三味線や太鼓、唄、日舞が必須のようでした。
実際に有田には日舞の先生やお花の先生、三味線の先生、お謡いの先生などたくさんのいわゆる「趣味」の先生がたくさんいらっしゃいます。
昔の子どもたちは塾に通うように三味線や日舞を習いに行っていたそうです。
(私の親の時代はまだまだ多かったようです。)
有田皿山三味線隊のみなさんはそんな時代を知る方々。
でも「昔は三味線の音が響いて良かったね。」と昔を懐かしむだけではなく、
若い人にも有田の三味線文化を伝えたいという想いを持ってらっしゃいました。
一応、私も三味線隊の一員でもあるので(三味線は弾けませんが・・・・)その想いをどうにかして活かしたいと思い、今回子どもたちのおくんち教室を行うことにしたのです。
子ども時代に三味線や太鼓を体験することで、大人になってからは有田のおくんちに少しでも愛着を持ってくれたら、
大人になってからでいいので三味線や太鼓を又習ってみたいと思ってくれたら、
それより何より、有田を誇りに思ってくれるようにと三味線隊のみなさんと私たちは願っています。
今日は初めて三味線や太鼓に子どもたちが触れました。
子どもの体には三味線は大きくて重たい楽器です。
それでも一生懸命に練習してくれましたよ。
ほとんどの子供たちが「さくらさくら」のワンフレーズは弾けるようになりました。
おくんちで皆さんに披露しますので、楽しみにしておいてくださいね。




Posted by On y Va! at 21:26│Comments(0)
│べんじゃらきっず