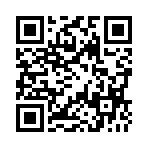有田学講座
2011年11月21日
女性懇話会さん主催の有田学に参加してきました。講師は竹田市の志賀先生。今回も私流にまとめています。解釈が違ったらごめんなさい!!!
 有田学 11月21日@有田町生涯学習センター視聴覚室
有田学 11月21日@有田町生涯学習センター視聴覚室
主催 有田町づくり女性懇話会
これからは経済至上主義の延長線上にはない。
「これからの有田」
情報発信するためには 地域を知る事、情報を精査する事が必要。 (からんころんの様に)
からんころん製作スタッフは20~60代後半。女性3分の1、行政が3分の1。民間と行政が協働できている珍しい事例として紹介された。視察が多かったが、泊るのは別府や湯布院等になっていた。視察は有料や竹田に泊まる事を条件にしたが、行政から無料にして欲しいと言われた。しかし、見えないものは無料という考え方が行政にはある。しかし、ただではない。
地域にあるものをどうやって知るかが大切。
景気は良くならない。人口が少なくなっているのだから良くなるはずがない。
海外に売るにしても円が高すぎで売れない。(ウォンは安いから売れている。TPFを結んでいるからではないハズ。)
物が動かなくなっている。
機械化、効率化する。短時間にコストをかけずに造るのは高度成長時代。
効率化ではなく、手を多くかけ、知恵を使って作る物が売れる→北欧、雇用能力の高い労働集約型の産業、業種が。よりいいものを限られた人たちにキチンと売る。
ではこれからの有田はどうする???
これまでの400年を磨くことでこれからの400年を磨くことになる。
何を守り、何を磨いてきたのか?それを明確化していく必要がある。未来からの逆算で物を考える。今している事が来年どうつながるのか、来年した事が10年後どうつながるのか?それが100年後どうなるのか?子どもたちの未来を考えていく事必要がある。
からんころんは5つの事業部があった。
食べていくためには (産業)
文化を育てるためには (文化)
環境を整えるには (環境福祉)
総務
情報センター
それぞれが竹田がどうあるべきがを毎週考えた。ブレストの中から深く考えていくことで高齢者でもできる産業ができてきた。(どじょうとわさび)高齢者から若者へ世代交代できるようにする。加工して商品として出すことでほかの産業とかかわりが出てくる(←上勝と一緒)
自分たちとほかの産業が繋がる事で消費者をここに呼ぶ事が出来る。
文化を守る事が100年後の町を守る事になる・・・ex.松江市
400年祭が見ているものは何??
有田が良くなるための評価基準は?
どうなりたいか?とどうなれるは?違う。
ミレーの絵を見て・・・・農業は地域を耕し、維持し、人間形成のために必要なものであった。
お金を落として欲しいから観光をするのでは地域は良くならない。
地域の役割・・・自助、共助ができなくなり公助だけになっている。これから先のまちづくりは行政と地域とNPO法人などとの協働が必要。
プランを作り→町→県→財務省→予算が下りる。地域のプランを練って、活動する覚悟を決めて具体的に絵にして出すことが必要。企画書を作る事。それから市町を説得をする。まちを良くしていくトレーニングになる。
優先順位をつけること。
・予算的に可能か?
・急ぐもの、急がないものの見極め。
日本の文化を守るためにしなければならない事…道具を作る人を守る事。
・効果の高いもの。
順番が変わる事でコストが全く変わってくるものがある。
・今でできること。
行政を動かすための時間を考えることも必要。
具体的に話せなければならない。評論家はいらない
よそから来てもらえるようなまちにするには…児童福祉→高齢者福祉→知的・精神・障碍福祉→環境→文化に理解にあるまちか?
産業振興
産業のためだけにあるわけではない。理想的な空間が産業と関わりがあるはず。
商店街とコミュニティ維持。
被災地での仮設の商店街。
商店街は地域のコミュニティの拠点であるべき。道路が生活文化の中心になっているのがヨーロッパ。日本は経済効率のためにコミュニティが無視されてきた。楽しみと情報を共有できたのが商店街であった。御用聞き、子どもを預かる、老人を預かる、障碍者施設、少数者を理解するための場であっていい。
道路、路地が生活全体の情報交流スペースであると考えることで異業種の交流とお金も生まれるはず。
「移ろい」の意識。
共有と私有の空間の移ろい。小布施。
営業戦略
経済は成長しない!大前提。輸出をすることで利益を上げてきていたのは一部の企業、経営者、投資家だけ。今のシステムでは輸出で経済は活性化できない。消費をする層が増えることでしか経済は良くならない。
北欧が見本なのではないか?
エネルギー、食料等全てのものの持久力を上げていく事なのではないか? シバを刈る→エネルギーを得る→里山の保全
ネット販売、カタログ販売は必要。ただし、この地域に来てもらえるような仕組みを作らない限り、一部の企業だけが儲かるだけで、地域の全ての産業が儲からない。
行政と首長はできない事がある。
地域を良くしていった人たちは理解されない。
先人の苦労などがあったから今の文化がある。今、理解されないという苦労をしても今しなければならないという強い想いがあるか?努力できるか?それを支える事が地域の文化力である。
「までいの力」飯館村の本
飯館村に比べるとどこももっと楽。
昔の人に比べるともっと楽。
だからもっと頑張らなければいけない。頑張る事が出来るはず。
江戸時代食料が増えなければ人口は増えない。だから開拓する。はげ山に木を植えることで水を得、食料を得る事が出来た。そのために1代は苦労する。そのことで子孫の生活を支え、つなげてきた。私達が今、子孫に残せるものは?と考え、行動に移さなければならい。
この講座は食事つきです。
もちろん、小路庵を運営されている女性懇話会さんのお手製のお弁当。
めっちゃ美味しかったです。
いつも素敵な方々です。
 有田学 11月21日@有田町生涯学習センター視聴覚室
有田学 11月21日@有田町生涯学習センター視聴覚室主催 有田町づくり女性懇話会
これからは経済至上主義の延長線上にはない。
「これからの有田」
情報発信するためには 地域を知る事、情報を精査する事が必要。 (からんころんの様に)
からんころん製作スタッフは20~60代後半。女性3分の1、行政が3分の1。民間と行政が協働できている珍しい事例として紹介された。視察が多かったが、泊るのは別府や湯布院等になっていた。視察は有料や竹田に泊まる事を条件にしたが、行政から無料にして欲しいと言われた。しかし、見えないものは無料という考え方が行政にはある。しかし、ただではない。
地域にあるものをどうやって知るかが大切。
景気は良くならない。人口が少なくなっているのだから良くなるはずがない。
海外に売るにしても円が高すぎで売れない。(ウォンは安いから売れている。TPFを結んでいるからではないハズ。)
物が動かなくなっている。
機械化、効率化する。短時間にコストをかけずに造るのは高度成長時代。
効率化ではなく、手を多くかけ、知恵を使って作る物が売れる→北欧、雇用能力の高い労働集約型の産業、業種が。よりいいものを限られた人たちにキチンと売る。
ではこれからの有田はどうする???
これまでの400年を磨くことでこれからの400年を磨くことになる。
何を守り、何を磨いてきたのか?それを明確化していく必要がある。未来からの逆算で物を考える。今している事が来年どうつながるのか、来年した事が10年後どうつながるのか?それが100年後どうなるのか?子どもたちの未来を考えていく事必要がある。
からんころんは5つの事業部があった。
食べていくためには (産業)
文化を育てるためには (文化)
環境を整えるには (環境福祉)
総務
情報センター
それぞれが竹田がどうあるべきがを毎週考えた。ブレストの中から深く考えていくことで高齢者でもできる産業ができてきた。(どじょうとわさび)高齢者から若者へ世代交代できるようにする。加工して商品として出すことでほかの産業とかかわりが出てくる(←上勝と一緒)
自分たちとほかの産業が繋がる事で消費者をここに呼ぶ事が出来る。
文化を守る事が100年後の町を守る事になる・・・ex.松江市
400年祭が見ているものは何??
有田が良くなるための評価基準は?
どうなりたいか?とどうなれるは?違う。
ミレーの絵を見て・・・・農業は地域を耕し、維持し、人間形成のために必要なものであった。
お金を落として欲しいから観光をするのでは地域は良くならない。
地域の役割・・・自助、共助ができなくなり公助だけになっている。これから先のまちづくりは行政と地域とNPO法人などとの協働が必要。
プランを作り→町→県→財務省→予算が下りる。地域のプランを練って、活動する覚悟を決めて具体的に絵にして出すことが必要。企画書を作る事。それから市町を説得をする。まちを良くしていくトレーニングになる。
優先順位をつけること。
・予算的に可能か?
・急ぐもの、急がないものの見極め。
日本の文化を守るためにしなければならない事…道具を作る人を守る事。
・効果の高いもの。
順番が変わる事でコストが全く変わってくるものがある。
・今でできること。
行政を動かすための時間を考えることも必要。
具体的に話せなければならない。評論家はいらない
よそから来てもらえるようなまちにするには…児童福祉→高齢者福祉→知的・精神・障碍福祉→環境→文化に理解にあるまちか?
産業振興
産業のためだけにあるわけではない。理想的な空間が産業と関わりがあるはず。
商店街とコミュニティ維持。
被災地での仮設の商店街。
商店街は地域のコミュニティの拠点であるべき。道路が生活文化の中心になっているのがヨーロッパ。日本は経済効率のためにコミュニティが無視されてきた。楽しみと情報を共有できたのが商店街であった。御用聞き、子どもを預かる、老人を預かる、障碍者施設、少数者を理解するための場であっていい。
道路、路地が生活全体の情報交流スペースであると考えることで異業種の交流とお金も生まれるはず。
「移ろい」の意識。
共有と私有の空間の移ろい。小布施。
営業戦略
経済は成長しない!大前提。輸出をすることで利益を上げてきていたのは一部の企業、経営者、投資家だけ。今のシステムでは輸出で経済は活性化できない。消費をする層が増えることでしか経済は良くならない。
北欧が見本なのではないか?
エネルギー、食料等全てのものの持久力を上げていく事なのではないか? シバを刈る→エネルギーを得る→里山の保全
ネット販売、カタログ販売は必要。ただし、この地域に来てもらえるような仕組みを作らない限り、一部の企業だけが儲かるだけで、地域の全ての産業が儲からない。
行政と首長はできない事がある。
地域を良くしていった人たちは理解されない。
先人の苦労などがあったから今の文化がある。今、理解されないという苦労をしても今しなければならないという強い想いがあるか?努力できるか?それを支える事が地域の文化力である。
「までいの力」飯館村の本
飯館村に比べるとどこももっと楽。
昔の人に比べるともっと楽。
だからもっと頑張らなければいけない。頑張る事が出来るはず。
江戸時代食料が増えなければ人口は増えない。だから開拓する。はげ山に木を植えることで水を得、食料を得る事が出来た。そのために1代は苦労する。そのことで子孫の生活を支え、つなげてきた。私達が今、子孫に残せるものは?と考え、行動に移さなければならい。

この講座は食事つきです。
もちろん、小路庵を運営されている女性懇話会さんのお手製のお弁当。
めっちゃ美味しかったです。
いつも素敵な方々です。